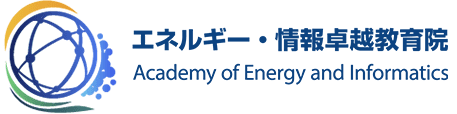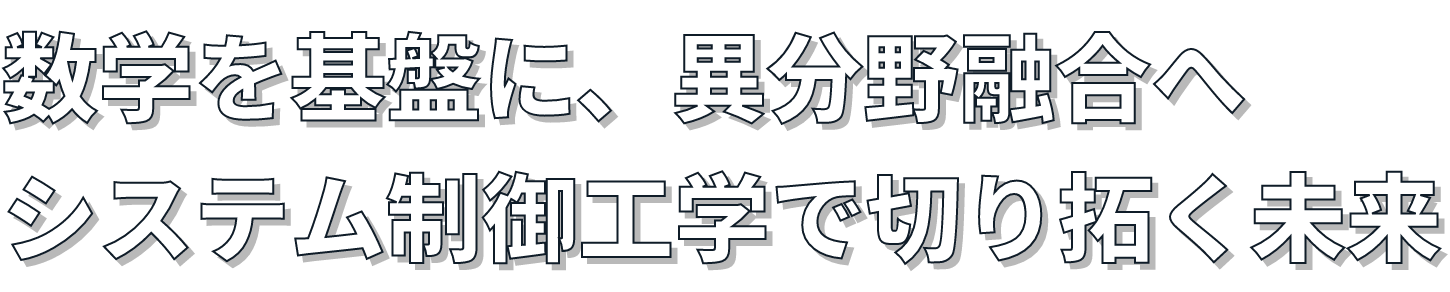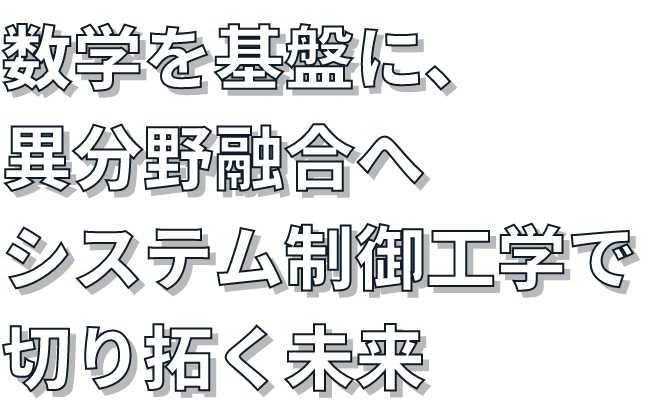工学院 システム制御系
システム制御コース(博士課程)
西野 択さん
早期卒業から博士課程へ
システム制御工学で電力系統の安定化に挑む
2018年4月に東京工業大学(当時)第4類に入学しました。学部時代から博士課程に進むことをめざし、少しでも早い時期に博士課程をスタートさせたかったため、学士課程で早期卒業を希望し勉学に励みました。その結果、早期卒業の要件を満たすことができ、2021年9月に学部を卒業し修士課程に進みました。
2023年9月、修士課程を修了して博士課程に進学し、現在、工学院システム制御系システム制御コースに所属しています。システム制御工学とは、世の中のさまざまなシステムを数理モデルとして表現し、安定性などさまざまな特性を数理的に明らかにする学問です。その応用対象は多岐に渡り、ロボットやドローン、自動運転車のみならず、電力システム、交通システム、原子時計の時刻同期システムなどが挙げられます。
現在の電力業界は、脱炭素社会の実現に向け火力発電から太陽光発電などの再生可能エネルギーへの転換を進めています。しかし、再生可能エネルギー電源は従来の火力発電と異なり、出力変動が大きいことや、系統の安定性を維持するための「慣性力」が不足するなどの問題が懸念されています。
そこで、私の研究では、これらの課題を解決するために、自身の研究では系統安定度の解析と、その解析手法に基づく次世代インバータ制御の開発を進めています。将来的には、GFMインバータの実用化や、慣性力の価値を定量化する数理モデルを構築し、電力市場における新たな制度設計の構築に貢献できればと考えています。


研究と学びを加速させるために
「エネルギー・情報卓越教育院」に所属すると、その名の通り、エネルギー分野に関わる学生や企業の方々と交流を持つことができます。
私の研究テーマは電力系統の運用ですが、多岐にわたるエネルギー技術と密接に関連しています。インバータ制御には燃料電池、風力、太陽光発電の知識が不可欠であり、同期発電機の数理モデル化には火力、水力、原子力の理解が必要です。近年は、アンモニア混焼や水素発電、新たな原子力制御など技術革新が著しく、電気自動車や水素輸送など送電以外のエネルギー運搬も進展しています。本教育院での学びを通してエネルギー業界全体の動向を注視することは、今後の研究方針に非常に有用であると考え、志望を決めました。
また、研究室の指導教授や先輩から登録を強く薦められたこと、本教育院ではエネルギー分野に加え、これからの時代に必要な情報技術や機械学習、統計などについても学べること、「国際フォーラム」で海外に行く機会があり、自身が苦手な英語にふれる環境にあえて身をおくことに意義を感じたことも、志望理由のひとつです。
数学を基盤に未知なる領域へ
「エネルギー・情報卓越教育院」で広がる視野

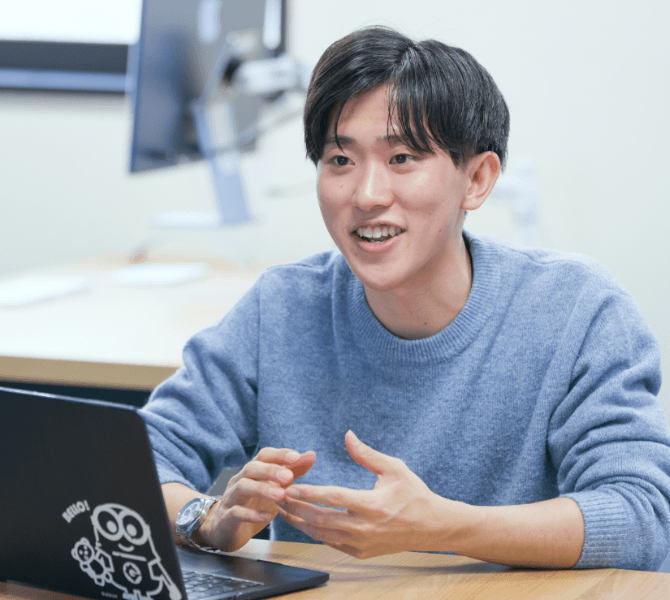
「エネルギー・情報卓越教育院」には化学系や電気電子系の学生が多く、多様な専門分野の学生と交流できます。自身の専門であるシステム制御だけでなく、燃料電池や電力設備設計など普段は触れる機会のない研究にふれ、互いに議論することで新たな視点や知識を得ることができました。
先ほど申し上げたように、システム制御工学は、数学を基盤にあらゆるシステムを数理モデル化し、分析・制御する学問であり、何色にも染まらないところが大きな特徴だと考えています。私の研究は電力系統に焦点を当てていますが、本教育院での学びを通して、システム制御工学を新エネルギーの運用方法の確立など、現在のエネルギー分野が抱える課題解決に活用し、新たな価値を創造したいと考えています。この分野の“強み”である数理を基盤に、さらなるシナジーを生み出せていければと考えています。そのためにも、今後も異分野の学生と積極的に交流していきたいですね。
マルチスコープの授業の中で特に印象深かったのは、ビッグデータ科学スコープの授業です。本学の大岡山キャンパスに構築されたデジタルツイン“Ene-Swallow®”を用いたエネルギーデータ解析は、実際のビッグデータ活用を体験できた貴重な機会でした。情報化が進む現代において、電力分野でもデータ活用の重要性が増しつつあります。エネルギー分野の一端を担う研究者として、情報分野の知識を深める重要性を改めて強く感じました。
失敗を恐れずに挑戦
国際フォーラムで得られたかけがえのない経験
「エネルギー・情報卓越教育院」の研究や活動を通じて最も自身の成長を感じるのは、私の場合、「国際性」です。本教育院では、年に一回、海外連携機関との国際的な研究交流活動を通じ、国際性や国際協働スキルの修得を目的に「国際フォーラム」が開講されます。今年度(2024年度)は「海外の大学に1週間滞在し、自身の研究内容と滞在先の研究内容より共同研究を生み出すための議論を行う」という内容で、単身でロンドンに渡りました。一人で海外に行くのは初めてだったのに加え、英語は片言で会話ができる程度。滞在一日目は、買い物をするだけでもひと苦労でした。それでも一週間滞在するうちに徐々に英語が聞き取れるようになりました。
その後、帰国し成果報告会を行いました。もちろん英語です。聴講して下さった教員の中には化学系専門の海外教員もおり、分野違いや、私の英語力不足などが重なり、なかなか伝えたいことが伝えられず苦労しました。しかし、その先生は私が答えられるよう時間をかけていねいに質問してくださり、なんとか伝えることができました。
社会に出ると、商談相手が必ずしも親身に話を聞いてくれるとは限りません。しかし、本教育院のような組織では、先生や他の学生が理解しようと歩み寄ってくれる環境の中で、説明能力やコミュニケーション能力を磨くことができます。これは、社会に出る前に自分自身の課題を克服するための貴重な機会だと思います。本教育院に在籍しているうちに、少しでも難しいことに挑戦して失敗や困難を経験し、それを乗り越えることが、自身の成長につながると考えています。
本教育院は、経済的支援があることも大きな特徴のひとつですが、このような「国際フォーラム」の旅費や滞在費もすべて支給してくださり感謝しかありません。
研究職か、企業人か?
問題解決能力を活かし、可能性を追求


自身の将来については、現在も悩んでいます。昨年、本教育院のプログラムで企業のメンターの方と面談する機会をいただき、今年度の秋と冬には研究所や企業のインターンシップにも参加しました。企業のインターンシップでは、電力の中枢機関である給電所などで使われる解析ソフトの開発に携わりました。こういった研究機関に就職すれば、自分が開発したものが社会で直接役立つことを実感できるのではないかと感じました。
一方で、アカデミアの道を選択した場合は、数学を基軸にシミュレーションや理論研究に没頭できるだけでなく、自分の興味に合わせてさまざまな分野に挑戦できると考えています。例えば、電力系統の研究で得た知識を交通システムや他の分野のネットワーク解析に応用することも可能です。研究費を獲得し、自由に研究を進められるのは、アカデミアならではの魅力だと思っています。
現段階では研究職のほうが自分に合っているように感じていますが、なるべく早めに方向性を定め、これまでの研究で培った問題解決能力を活かして幅広い分野で活躍できる人材となることを目指していきたいです。
研究の意義を社会へ
「エネルギー・情報卓越教育院」で磨く実践力
博士課程に進む学生にとって、「エネルギー・情報卓越教育院」に所属することは大きなメリットがあると思います。経済的支援はもちろん、異分野の学生や企業、海外大学との交流を通して、研究者として必要な視点やスキルを磨くことができるからです。また、企業のインターンシップなどで実際の産業界の課題やニーズを体験でき、研究室での研究だけでなく、社会とのつながりを意識することで、より実践的な研究活動につながります。
さらに、博士課程では、研究申請書の作成や研究費獲得など、研究の意義を社会に伝える力が求められます。以前、企業のインターンに参加した際、部長の方から「博士学生のうちから『現在の産業界のどこに課題があるのか?自身の技術が既存技術とどう違うのか?それは誰が利益を受けるのか?どういうビジネスにつながるのか?』を意識しなさい」と言われたことがあります。本教育院で自身の専門分野以外の学びに触れ視野を広げておくこと、異分野の研究者に自身の研究価値を伝える練習を重ねておくことは、将来のキャリアにおいて、大きな強みとなります。
「エネルギー・情報卓越教育院」は、研究者としてのスキルアップだけでなく、社会との繋がりを意識した研究活動を支援する場所です。自身の研究を社会に役立てたい方は、ぜひ、この機会を活かしてほしいです。
工学院 システム制御系
システム制御コース(博士課程)
西野 択さん

工学院 システム制御系
システム制御コース(博士課程)
西野 択さん
- 2018年4月
- 東京工業大学(現東京科学大学)第4類入学
- 2019年4月
- 工学院システム制御系
- 2019年4月
- システム制御コース(修士課程)
- 2023年4月
- エネルギー・情報卓越教育院 登録
(2025年2月取材)